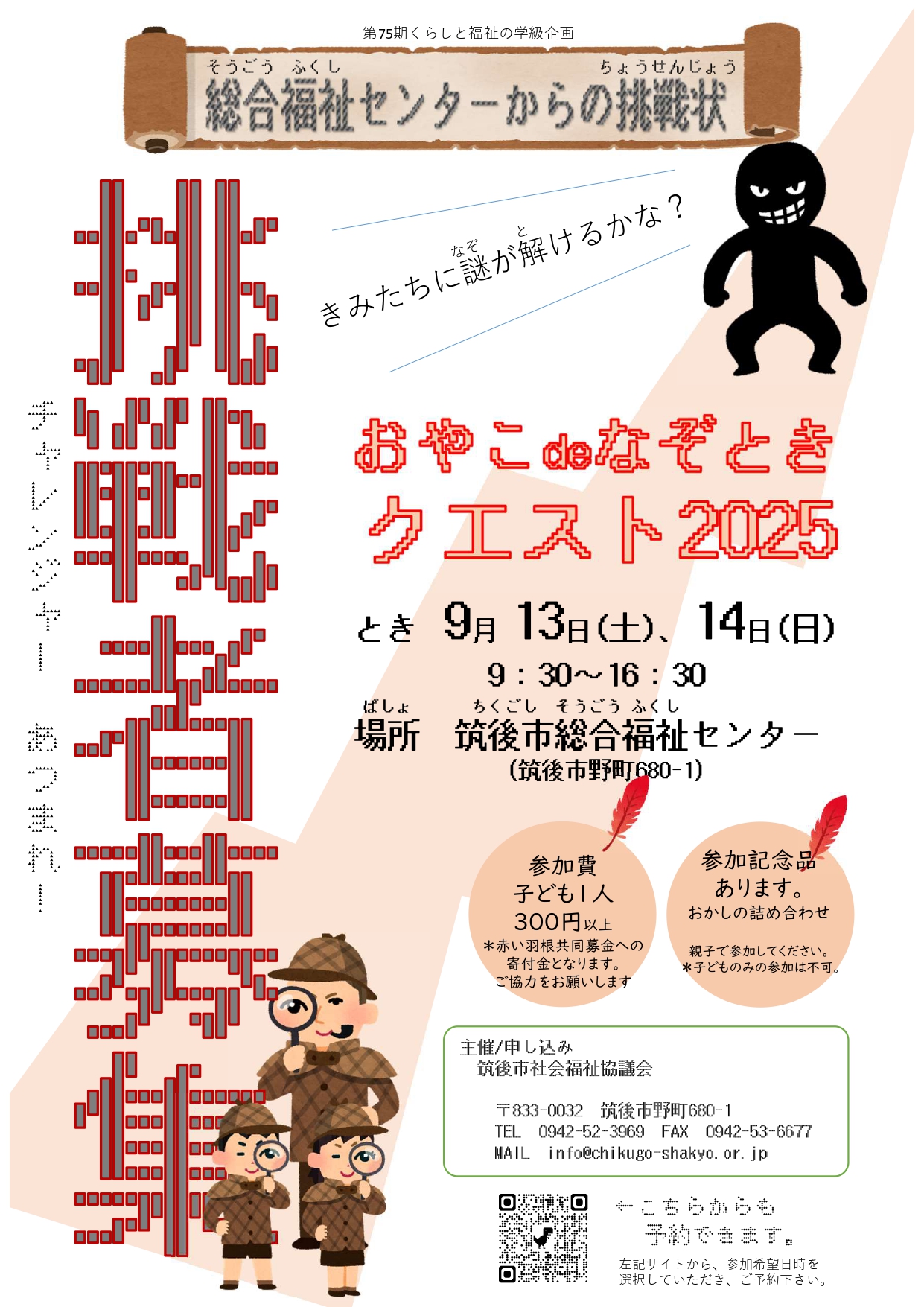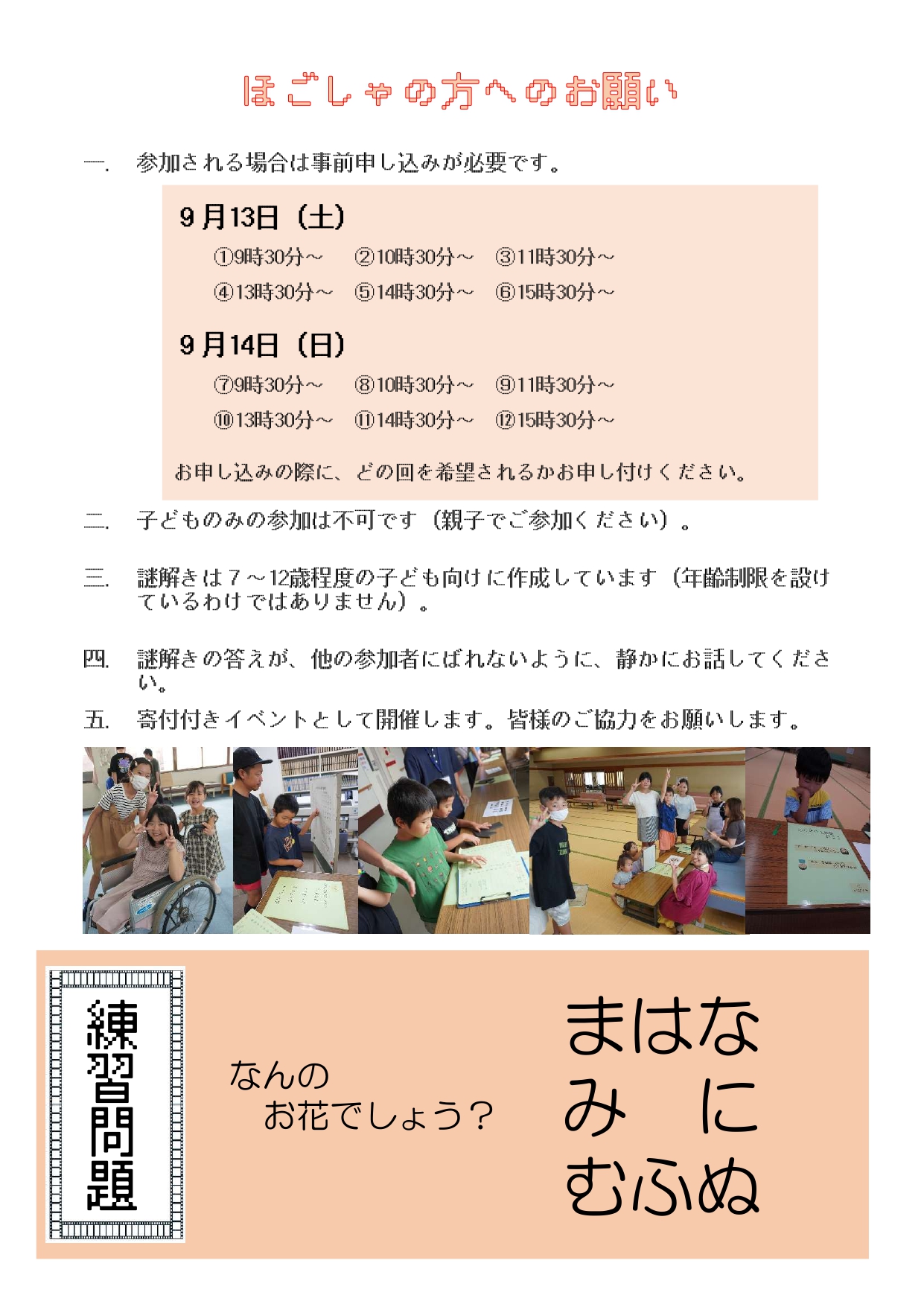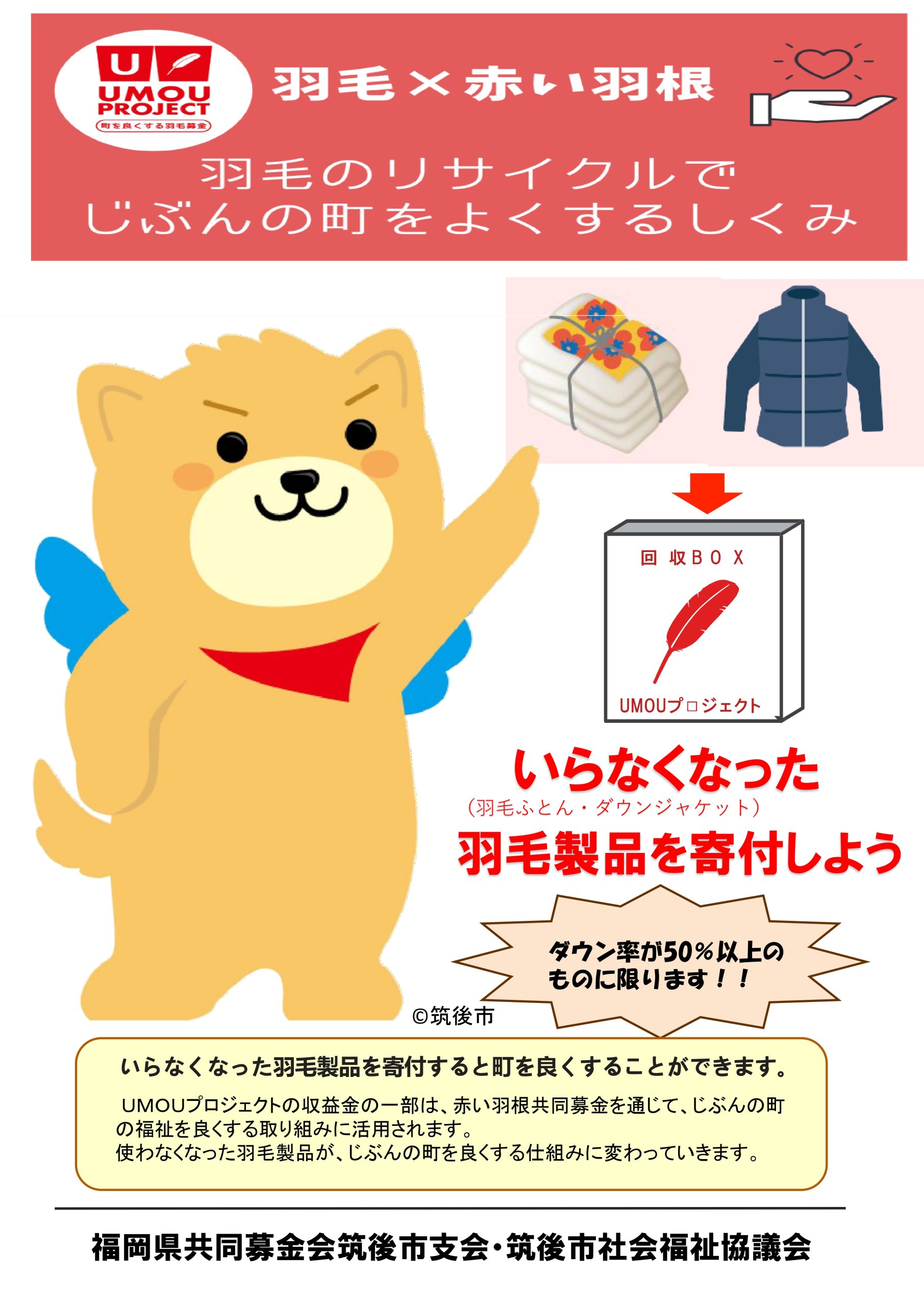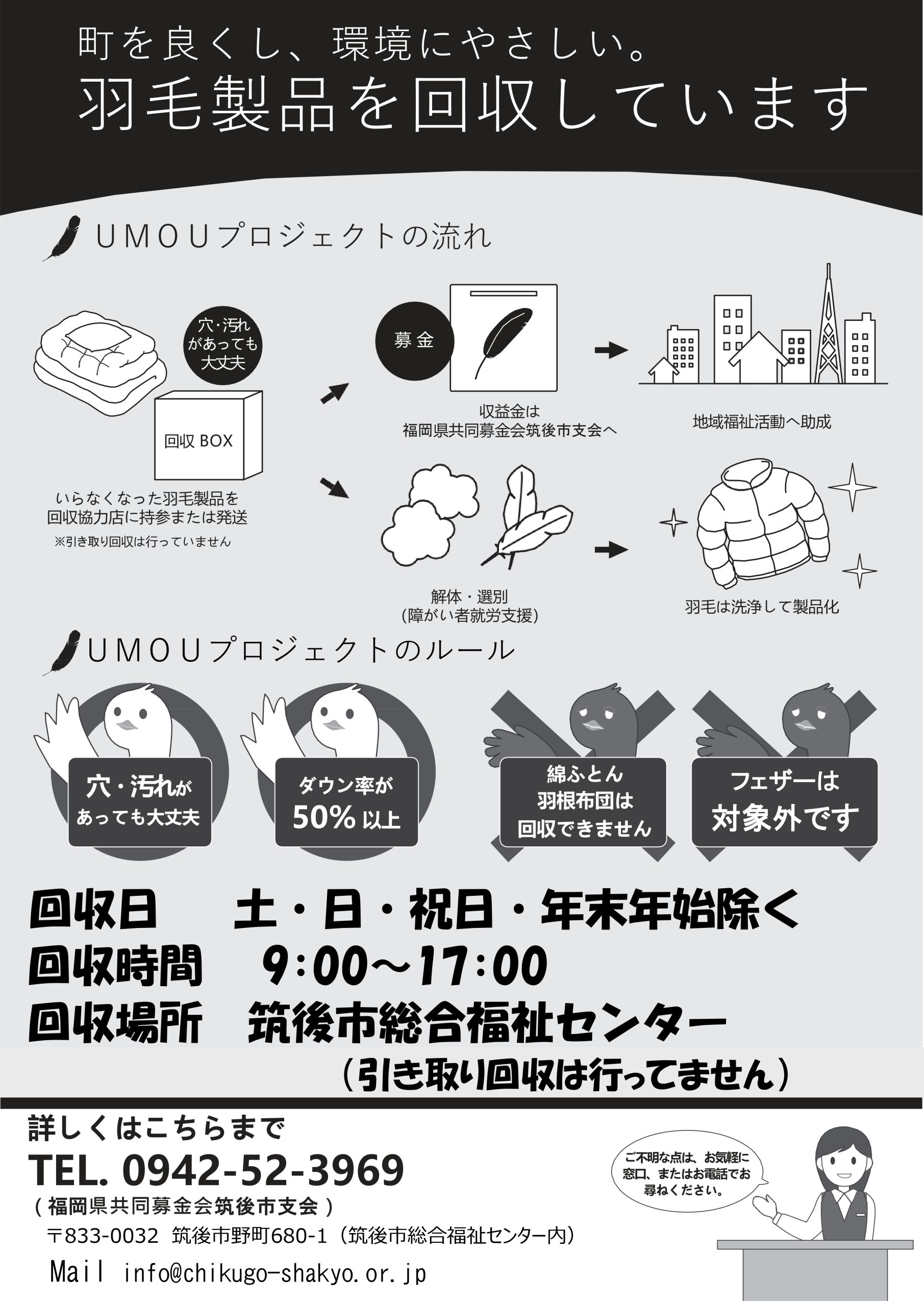20年以上、夫を介護している女性の言葉です。
介護家族の会の会員で、ずっとお話をお聴きしていました。
「とにかく夫を嫌いにならないように、がモットー」「家族会で話すと、すぐ分かってもらえるので、ありがたい」や、「『孫が成人式を迎えるまで、オレは生きるつもりだ』と夫は言っている」という話もお聴きしていました。
なので、「夫が亡くなりました」の連絡に驚くばかりでした。
訃報を聞いた他の会員は「長い間、お疲れさまでした」と言われました。そして、長年の介護を労う言葉が寄せられました。そして、女性からは感謝の言葉が返されていました。
家族の介護という共通点があるからこそ、「分かってほしいだけ」が自然とできるし、介護の頑張りや苦労を理解している人がいることが、介護を乗り切る力になったのかもしれない。
支援は大事です。そして、理解と共感は、もっと大事なのかもしれません。 (善)