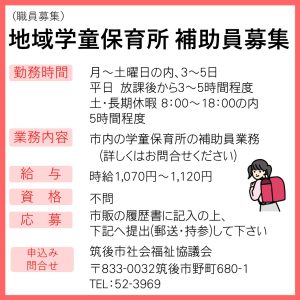社協だより「人として」2月号を発行しました。
056c2b7c10b70c0e9f66b99500a4b817在宅福祉課 嘱託職員募集のお知らせ
筑後市社会福祉協議会【嘱託職員募集】のお知らせです。
私たちと一緒に、福祉のまちづくりを進めていきませんか?
嘱託職員(在宅福祉課)
| 募集職種 | ホームヘルパー(嘱託職員) |
|---|---|
| 募集人数 | 若干名(面接等により決定) |
| 資格 | 普通自動車運転免許(AT限定車可) 介護福祉士、ホームヘルパー2級、介護職員初任者研修・実務者研修修了者のいずれか |
| 仕事内容 | 筑後市内・近郊の利用者宅等を訪問し、身体介護や家事支援、移動の支援を行います。 ・訪問は自家用車を使用していただきます。 ・パソコンソフトでの記録等の事務業務あります。 |
| 労働条件 | 6:30〜22:00の間の7.75時間のシフト制 週休2日(曜日については採用後決定) |
| 賃金等 | 基本給 238,700円〜245,800円(昇給あり) [手当] 通勤手当:距離に応じて社内規定により支給、ガソリン手当:10,000円 [賞与] 年2回(前年度実績:計2.0ヶ月分) |
| 応募 | 履歴書、資格証のコピー |
| 採用試験日 | 随時 |
| 採用年月日 | 随時(要相談) |
| 問い合わせ先 | 筑後市ホームヘルプサービス 採用担当 TEL:0942-52-9016 |
「誰もが安心して暮らせる社会へのヒント」
本号の作成にあたり、音訳広報の利用者にインタビューをしました。そこで感じたのは、「直接話を聴くことの大切さ」です。
当たり前に得られると思っていた情報を、得られずに不便を感じている人がいることを知りました。また、「もっと知りたい」と思う情報は、一人ひとり違うことにも気づかされました。少し想像すれば、分かりそうなことが、実際には分かっていなかったのです。
利用者の声を直接聴くことが「何とかしたい」「できることはないだろうか」と考えるきっかけとなり、誰もが安心して暮らせる社会のヒントとなるのではないでしょうか。
「今、元気で困っていないから大丈夫」ではなく、「高齢になっても、病気や障害があっても、自分らしく生きていくことができるから大丈夫」。そう思える地域を目指していきたい…。
生きづらさを抱えながら暮らしている人の声を、みんなの気づきへと変え、支え合えるまちにつなげていきたいです。 (実)
社協だより「人として」1月号
社協だより「人として」1月号を発行しました。
1c5c1291326f7e6ef49fa6472f75f1aa「生きづらさの正体は、子どもの頃にあった」
「やっと自分の人生が始まる」。
久しぶりにきょうだい会に参加した女性の言葉が心に刺さりました。
障害のある姉に親の関心が向き続けた幼少期。「自分は血のつながりがないのでは」と感じるほどの孤立感があったと言います。また、職業も「家族の助けになること」が選択の基準に。
このように、自分を後回しにしてきた彼女は、「家族にとって良いこと」が生きていく上での基準になっていました。そして、心の底には親への抑えきれない思いが常にあったと言います。
こうした日々が積み重なり、大人になってうつ病と愛着障害と診断されました。
そんな彼女の転機は、「自分のために生きていい」という主治医の言葉。そして母の「あなたはあなたの人生を生きてほしい」という一言でした。
「自分が幸せになるための道を選ぶ。それは初めての経験」と彼女。
彼女の人生を心から応援したい。
そして。幼少期の経験が大人になった時の生きづらさになっている人は多いのでは…、とも思うのです。(善)
社協だより「人として」12月号
社協だより「人として」12月号を発行しました。
33f6f74079f98d82a58141878bbf1357「戦後80年。想いを受け継ぎ、生きていることそのものを大事にできる社会へ」
今年は戦後80年。メディアを通して多くのことを目にしました。
特に印象深かったのは、「亡くなった人たちのために、生きている自分にできることは…」と、身近な人を亡くし、さまざまな想いを持ちながら必死に戦後を生きてきた方達です。
学生時代に学んだ戦争の悲惨さ。当時からその恐ろしさを、受け止め切れずにいました。
しかし今回改めてその恐ろしさと向き合うと、戦後を生きる方たちのさまざまな苦しみを感じることができました。
同じ時間を生きていることを、ただただ喜び、それぞれが自分らしく安心して暮らせるように…。互いに支え合い、繋がりあって暮らせるように…。戦後100年、200年と言い続けられるように…。未来を生きる人たちが、平和に明るく暮らしていけるように…。
それらを叶えるために大切なのは、戦後必死に生きてきた方達の想いを受け継ぐことです。
社会に役立つことで生きていい、ということではなく、生きていることそのものを大事にできる社会を育むことが必要だと思いました。 (実)
社協だより「人として」11月号
社協だより「人として」11月号を発行しました。
cc51191ceffdc5dba48cdfea7bd40de4ダブルケア「理解」の大切さ
「高齢者の見守り訪問をするとき、子どもさんと同居している家庭は安心していましたが、本当は、大変な思いをしているかもしれないと感じました」本号で紹介した、佐藤さんの講演を聞いた、参加者の感想です。
実は私も、講演を聞いて、はっとした一人でした。
私の祖母が脳の病気で倒れた時、母は第一子を妊娠中。出産後、慣れない土地で介護と育児を同時に担うことになりました。
当時は、介護保険などの制度もなく?家のことは嫁がするのが当たり前?という時代でした。
障害が残り、母や私たちの存在を認識できず「よそ者がいる」と怒り続ける祖母を介護しながらの家事や子育ては、10年以上続きました。母の姿を見て、「大変そうだ」と感じていました。
しかし、佐藤さんのお話を聞くまで、自分の母が体験していたそれが、「ダブルケア」と結びついていませんでした。
「ダブルケア」がどのようなことをさすのかを「知る」ことが入り口だと思います。でも、大切なことは、自分の身近にあることとして「理解する」ことなのだと改めて感じました。 (中)