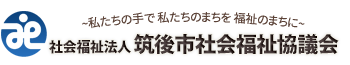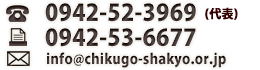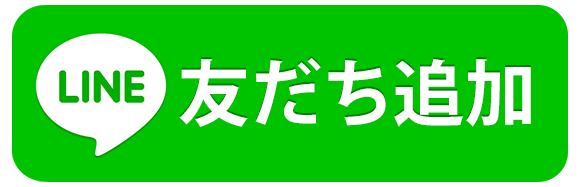「社会福祉協議会」について
私たち筑後市社会福祉協議会では、以下のことを大事にして活動を薦めていきたいと考えています。
社会福祉協議会は、1951年(昭和26年)に、それまで、社会事業協会、民生委員連盟、同朋援護会の3組織が統合し、新たな組織として誕生しました。これは、戦後の民主化政策の下で行われました。その4年前(1947年/昭和22年)には、共同募金会が発足していました。
新しい組織づくりにあたっては、学者や社会事業協会、厚生省幹部らがアメリカやドイツなどに学び、新しい理念を学んできました。「住民主体」、「コミュニティオーガニゼーション(地域組織化活動)」といった社会福祉協議会ならではの活動理念は、その発足以来、大事にされてきた基本的な考え方といえます。
市町村社会福祉協議会を基本的な活動組織体として捉え、上部機関には、都道府県社会福祉協議会、さらには、中央社会福祉協議会(名称は、以後変更され、全国社会福祉協議会と改称)がつくられています。 この社会福祉協議会発足にあたっては、地方から中央へ、との考え方がありましたが、実際には、逆な形で中央から地方へと組織化されてきました。これは、民主的な組織づくりのためには、下から上に組織化するという理念よりも、現実的に組織しやすいところから組織化していった結果、そのようになっていったものです。
社会福祉協議会発足に大きくかかわった人物としては、牧賢一氏(社会事業協会)、黒木利克氏(厚生省)が有名ですが、ここに、牧賢一氏が、『住民福祉のための社会福祉協議会活動』(1970)に記した「社会福祉協議会」を紹介し、社会福祉協議会がどのような組織としてつくられ、またどのような役割をもって活動する組織なのかを紹介したいと思います。
●第1に、社協は、他の団体・機関と違って、特定の保健福祉問題の解決を、活動の目的としていない。社協の特徴は、その地域社会で、何が早急に解決しなければならない活動であるかを見いだし、そしてその解決方策を考えようとする点であり、これが他の団体・機関との基本的なちがいの一つとなっている」
※社会変動などの結果起こってくる社会福祉問題を取り上げていくには、既存の機関・団体はあまり頼りにならない。やはり問題の担い手である住民が声をあげなければいけないのである。これが、「住民参加」という意味であり、住民の参加の度合いが高いほど、既存の機関・団体の既得権や専門家的狭量の弊害をさけることができる、ということから、さらに進んで、「住民主体」という考え方が生じてきたわけである。住民が主体となり、専門機関・団体は、これに援助・協力を与えるのだという考え方は、こうして生まれてきたのである。
なお、住民が声をあげるとか、参加するといっても、一人や二人では何の力にもならない。多数の人が参加し、協同してこそ大きな力を発揮することができるわけで、ここから地域組織化の必要性が生じてくるわけである。
社協のこのような働き… つねに地域の問題を見つけ出し、その解決策を考え、その実現のための活動(必要によっては自ら実施する)を進める… から、社協の基本的性格は、「福祉向上のための運動体」であるということもできるのである。
●第2に、社協は、地域の保健福祉問題を、地域住民の自主的な協働活動あるいは協同事業によって解決しようとする団体である、ということである。
※行政だけでやる、あるいは専門機関だけでやる活動だけでなく、住民自身が自主的、主体的に取り組んで地域全体の福祉環境を整えていく、高めていく活動(地区組織化活動)の必要性、意義を記述しています。
●第3に、地域社会の福祉増進のために、一般住民の声を結集し、世論を動かして、社会福祉制度の創設あるいは改善をはかろうとすることにある。
※地域の保健福祉問題を自主的協働活動や、協同事業によって解決しようと思っても、制度や専門機関がなかったり、あるいは不十分なため、効果があがらないということもよくある。こういう場合には、世論を動かし、政府(国、都道府県、市町村)にしかるべき処置をとってもらわなければならない。
このような活動を専門用語では「社会行動」あるいは「ソーシャル・アクション」といい、これは社協にとっては、これまで述べた二つの項目と並ぶ重要な目的である。
●第4に、住民福祉の関係のある公私の各種機関・団体の相互協力の場となるということがある。
※バラバラにある専門機関や団体をつなぎ、住民福祉のために連絡・協同する場となることが社協の重要なねらいの一つになっている。なおこの機能は、以前は連絡調整といわれ、社協の唯一の目的のように言われていたものであるが、現在では重点が変わり、用語としても、もっと積極的な「協働」というような言葉を使うことが多くなった。
以上は、牧氏が、社会福祉協議会関係者に伝えようとした「社会福祉協議会論」です。
あわせて大事にしていく社会福祉協議会活動の理念としては、「地域福祉論」があります
同志社大学の岡村重夫氏(故人)が、1974年に「社会福祉選書①」の「地域福祉論」に著された著書が日本で最初に出された「地域福祉論」の源流といわれています。
この理論の実現化を図るのことが、社会福祉協議会の大きな役割とも思っています。
以下、氏の論の要約を記します。
①社会福祉の基本的な機能を発揮し、その目的を達成するためには、その志向は、生活問題発生の根源としての地域社会に向けられなければならない。
②保護事業としての社会福祉の保護対象者のもつ生活上の要求を真に充足するためには、地域社会において彼のもつすべての社会関係を維持・発展させるような形で援助を与えなければならない。地域社会関係や家族関係を断ち切るような保護は、真実の社会福祉的援助にはなりえない。
③問題発生の事後的対策よりも、問題発生を予防する対策の方が合理的であることはいうまでもない。社会生活上の困難の発生を未然に防止したり、早期に問題を発見して軽症のうちに解決するような予防的効果をもつ社会福祉を発展させるためには、社会福祉は全住民を相手とし、地域社会の中に入り込んで、要求をつかみ、また地域社会における他の制度的機関とともに、地域社会施設の一部として組み込まれなくてはならない。
④国民の生活問題にかかわる社会制度や社会的施策の立案、実施、運営に対して、国民を効果的に参加させるためには、地域社会レベルにおける住民参加が必要である。社会福祉はその本質上、住民ないし援助対象者と同じ立場に立つものであるから、住民参加を援助するのに最もふさわしい地位にある。そして真に民主的な住民参加を可能にする地域社会こそ、社会福祉の最大の関心事である。
日本の社会福祉は、慈善事業・感化救済事業、社会事業、厚生事業、社会福祉事業、地域福祉と時代的な変遷を見せています。1970年代後半からは「個人の尊厳」を目標に、「人として」の存在の質が問われる時代になってきているように思えます。
しかし、地域社会には、まだまだ取り残された福祉課題があり、その中で社会的弱者として負担の多い生活を強いられている人たちも数多くあります。これらの人々の課題を掘り起こし、住民に提起し、住民と共にその解決策を探って、組織化し、運動化(住民参加)していく取り組みが、社会福祉協議会という組織に問われていることを肝に銘じたいと思っています。
「人として」(筑後市社会福祉協議会広報紙の題字)、だれもが尊重され、人間的なつながりの中で豊かに暮すことのできる「福祉のまちづくり」を創っていく・・・筑後市社会福祉協議会は、「私たちの手で 私たちのまちを 福祉のまちに」をスローガンに活動しています。