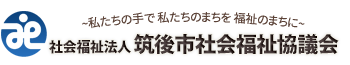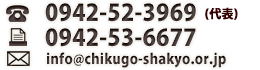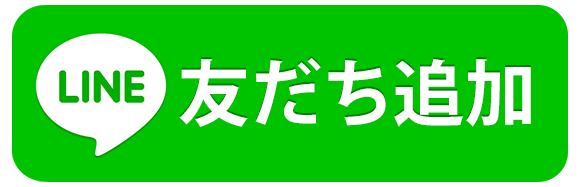「先生たちに知ってほしい吃音のこと」というリーフレットがあります。
吃音は、頭の中では分かっているのに、円滑に話せなかったり、スムーズに言葉が出てこない症状のことで、子どもの発症率は20人に1人と言われています。
そのリーフレットには、「時間がかかっても、話し終えるまで待ちましょう」「話し方よりも、話の内容に注目しましょう」とありました。
ということは、話の途中で遮られたり、話し方をからかわれ悔しい思いをした吃音者が多いということでは…。
また紙面には、「周囲に吃音を受け入れてもらえるかの不安」「からかいや偏見への恐怖」という吃音者の声も紹介されていました。
つまりは、「言葉が出ない」ことよりも、周りとの関わりの中に生きづらさがあるということになります。
今秋、吃音の青年を実習で受け入れました。彼にとって私は安心してどもれる人だっただろうか。問われているのは彼の吃音ではなく、「私」なのかもしれません。 (善)